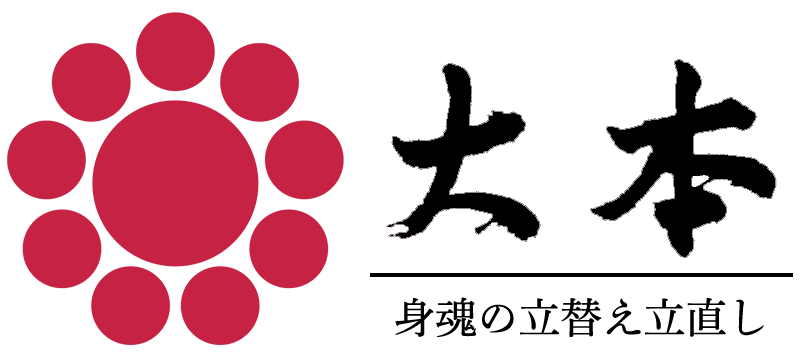大本にゆかりのある霊場が全国にあります。
高熊山(たかくまやま)

亀岡の聖地・天恩郷(てんおんきょう)から西へおよそ5キロほど行ったところにある霊山です。
出口王仁三郎聖師は明治31年(1898年)に神使(しんし)に導かれ、ここで1週間の修業を行いました。
地元では丁塚山(ちょうづかやま)とも呼ばれています。標高357メートル。
出口王仁三郎聖師は明治31年(1898年)に神使(しんし)に導かれ、ここで1週間の修業を行いました。
地元では丁塚山(ちょうづかやま)とも呼ばれています。標高357メートル。
瑞泉苑(ずいせんえん)

瑞泉苑に建つ聖師の歌碑
出口王仁三郎聖師の生家です。高熊山の麓、亀岡市穴太(あなお)にあります。
上田喜三郎(後の王仁三郎聖師)はここで明治4年(1871年)に生まれました。
上田喜三郎(後の王仁三郎聖師)はここで明治4年(1871年)に生まれました。
弥仙山(みせんざん)

綾部の聖地・梅松苑(ばいしょうえん)の北東およそ15キロほど先にある霊山です。
明治36年(1903年)に山頂の神社で出口なお開祖らにより岩戸開きの神事が行われました。
標高664メートル。どの方向からながめても三角形の山容をしているため、丹波富士とも呼ばれています。
明治36年(1903年)に山頂の神社で出口なお開祖らにより岩戸開きの神事が行われました。
標高664メートル。どの方向からながめても三角形の山容をしているため、丹波富士とも呼ばれています。
鉢伏山(はちぶせやま)

兵庫県の北部、鳥取県との県境付近にある標高1221メートルの霊山で、山頂には奇岩・怪岩が立ち並んでいます。
昭和21年(1946年)に王仁三郎聖師によって山開きが行われ、「陸(あげ)の竜宮」の奥の院として、大本の霊場に加えられました。
昭和21年(1946年)に王仁三郎聖師によって山開きが行われ、「陸(あげ)の竜宮」の奥の院として、大本の霊場に加えられました。
沓島・冠島(めしま・おしま)

若狭湾に浮かぶ二つの無人島で、綾部から見て北東(艮-うしとら)の方角にあります。
沓島には国祖・国常立尊(こくそ・くにとこたちのみこと。艮の金神ともいう)が、冠島にはその眷属の神々が、三千年の間、隠退されていた霊場です。
明治時代に沓島・冠島開きが行われ、ご神霊が綾部の聖地に迎えられました。
「くつじま」「かむりじま」と呼ぶときもあります。
沓島には国祖・国常立尊(こくそ・くにとこたちのみこと。艮の金神ともいう)が、冠島にはその眷属の神々が、三千年の間、隠退されていた霊場です。
明治時代に沓島・冠島開きが行われ、ご神霊が綾部の聖地に迎えられました。
「くつじま」「かむりじま」と呼ぶときもあります。
神島(かみじま)

兵庫県高砂市の沖合、瀬戸内海に浮かぶ小さな無人島で、綾部の西南(坤-ひつじさる)の方角にあります。
国常立尊の妻神・豊雲野尊(とよくもぬのみこと。坤の金神ともいう)が隠退されていた霊場で、大正時代に神島開きが行われ、ご神霊が聖地に迎えられました。
国常立尊の妻神・豊雲野尊(とよくもぬのみこと。坤の金神ともいう)が隠退されていた霊場で、大正時代に神島開きが行われ、ご神霊が聖地に迎えられました。
芦別山(あしわけやま)
北海道の夕張山地にある標高1727メートルの山で、国祖・国常立尊が隠退されていました。
芦別岳(あしべつだけ)とも呼ばれます。
芦別岳(あしべつだけ)とも呼ばれます。
宮原山(みやばるやま)
鹿児島県の喜界島(きかいじま。鬼界ヶ島ともいう)にある山で、豊雲野尊(とよくもぬのみこと)が隠退されていました。
大本は日本の、日本は世界の、縮図・雛形であり、大本・日本・世界の三段階あるので、これを「三段の型」といいます。
国常立尊(くにとこたちのみこと)や豊雲野尊(とよくもぬのみこと)が隠退されていた場所も各段にそれぞれ存在します。
国常立尊が隠退されていた場所は、艮の方角にある沓島・芦別山・日本列島で、豊雲野尊が隠退されていた場所は、坤の方角にある神島・宮原山・サルジニア島になります。
国常立尊(くにとこたちのみこと)や豊雲野尊(とよくもぬのみこと)が隠退されていた場所も各段にそれぞれ存在します。
国常立尊が隠退されていた場所は、艮の方角にある沓島・芦別山・日本列島で、豊雲野尊が隠退されていた場所は、坤の方角にある神島・宮原山・サルジニア島になります。
| 国常立尊 | 豊雲野尊 | |
|---|---|---|
| 大本 | 沓島 | 神島 |
| 日本 | 芦別山 | 宮原山 |
| 世界 | 日本列島 | サルジニア島 |